横断型人文学プログラム
- Home
- 横断型人文学プログラム
- 芸術文化論コース
芸術文化論コース
美術文化論

角山朋子先生による講義でした。
19世紀末から20世紀初めに流行したアール・ヌーヴォーは、自然の美しさを示す曲線や有機的表現を特徴としつつも、人工動力の発展に伴う躍動感も作風の一つです。アーツ・アンド・クラフツ運動の影響を受けたことで、生活芸術に関心を持ち、室内全体を美しくするような統合的な美的空間を作り出そうとした点や、近代技術に関心を持ち、ヴィクトール・オルタの建築に代表されるように装飾と機能性を融合させた点も特徴として挙げられます。
ブリュッセル、パリ、ナンシー、ミュンヘンなど、各地域のバリエーションにも注目しながら、近代初の国際様式といわれるアール・ヌーヴォーの作品の数々を見ていきました。
造形芸術の世界
① イントロダクション―造形芸術とは?―
コーディネーターの桑原俊介先生(本学文学部哲学科)による講義でした。
「造形芸術」の概念は、18世紀中葉に私たちの知る「芸術」の概念が成立した後、その下位区分として成立します。それまでにあった「絵画は詩のように、詩は絵画のように」という考え方が薄れ、詩や音楽に代表される聴覚的なもの、時間的なものから区別されてできたのが「造形芸術」です。
この輪講では、「造形芸術」を広く捉えて、絵画、彫刻、建築に留まらず、ファッション、写真、ゲーム、工芸についても扱っていくというお話でした。
② ファッション
跡見学園女子大学の深町浩祥先生による講義でした。
「ファッション」は本来、「材料をものに作り上げる」を意味し、現代においては「アパレル業界」(狭義)、「流行を伴う産業」(広義)を指します。そしてファッションビジネスは、他人と同じものが欲しい(標準化)、個性を表現したい(差別化)という人々の相反する願望を満足させるものであるとのこと。
さらに、ファッションビジネスは、芸術、自然、社会科学分野と連動していて、直観的な心の動きと論理的思考についての総合的な学び(時代や国によって異なる色に対するイメージや、事象の象徴性等についての理解)が必要であるというお話もありました。
③ 現代写真
写真家の大山顕先生による講義でした。
写真は時間をかけてじっくり見るものではなく、日常のなかにふっと割りこんでくるメディアであり、繰り返し目にすることで、以前とは見方が変わったり、見えていなかったものが見えたりするというお話がありました。
カメラは、「目にしているけど見ていない」ものをスルーしない装置として素晴らしい価値を持っているとのこと。
「写真がその人の個性や能力を表す」という幻想を打ち破る、をコンセプトに先生が企画された「うまくならない写真ワークショップ」についての興味深いお話も伺うことができました。
④ 建築

建築家の坂牛卓先生(東京理科大学)による講義でした。
建築デザインにおいて先生が重要視されているWindow(窓)、Frame(フレーム)、Flow(流れ)の3つのコンセプトについて、先生が手掛けられた建物の写真を見ながらお話を伺いました。
フィギュア性を失ってどこまでも伸びていき、壁と一体化、ないしは、壁と反転するような窓、道路からフレームに見立てた内部が見えるように設計されたリサイクル工場(ダストや音を出さないために、中の見えない箱のような形状にするのが普通)、建物の中に作られている流れ等、様々な発見がありました。
⑤ 天皇の図像

コーディネーターの桑原俊介先生による講義でした。
江戸の終わりまで最高宮司(祈る人)として世間から隠され、明治以降は、家長制度促進のために皆の父として人々から見られる存在になった天皇が、御真影を通して強力な権力行使を可能にした経緯について学びを得ることができました。
⑥ ビデオゲーム
美学・哲学の観点からビデオゲームを研究されている、京都大学の松永伸司先生のご登場です。
ビデオゲームのフィクションの特性(インタラクティブ、すなわち、プレーヤーの挙動に対応するかたちで表象が変化する)、ゲームメカニクス(制度、法律、建物、道具等による制約や意味付けを通して、人の行為を形作る、すなわち行為のデザイン)等についてのお話や、ゲームの実況動画を流しながらの解説は新鮮でした。
⑦ 現代アート

東京藝術大学の林卓行先生による講義でした。
色・形を重視するフォーマリズムと各ジャンルの独立を提唱するモダニズムとが結び付いて生まれた、物語性・宗教・政治から切り離した純粋な〈かたち〉に向き合うという考え方に対し、批判的な立場を取ったフェリックス・ゴンザレス=トレスと、彼が所属していたグループ・マテリアルの活動の軌跡を辿りました。
⑧ 工藝

東京大学の入江繁樹先生による講義でした。
民藝運動の父として知られる柳宗悦(1889-1961)が、実は民藝よりも工藝に価値を置いていたことを、柳自身の記述を手掛かりにしながら見ていきました。
柳にとって、かつての民藝が持っていた無心の美は美しさの規範以上のものではなく、彼が真に言わんとしているのは、民藝に代わる、民藝をモデルにした新しい工藝を生み出さなければならない、ということであるというお話でした。
音楽文化論

北里大学の安川智子先生による講義です。
テーマは「オペラを解体する」。
16世紀後半のフィレンツェには、「カメラータ」(「仲間たち」)と呼ばれる、古代ギリシャ文化(悲劇、音楽)の復興を目論むアカデミックなサークルがありました。サークル内では、「ギリシャ悲劇の詞はすべて歌われていた」という主張が支持され、音楽については、既存の合唱形式ではなく独唱形式(和声の部分は楽器が担当する)が推奨されます。こうした考えを論じ合うだけでなく、メンバーたちが実践に移したことで誕生したのがオペラです。
オペラは次第に、語りに音楽をつけたレチタティーヴォと、豊かな旋律に乗せて感情を歌い上げるアリアで構成されるようになりました。さらに時代を下ると、「すべて歌う」という当初の決まりから逸脱した、普通の台詞を含むオペラも出現します。
講義のなかでは、ヘンデル《ジュリアス・シーザー》(1724年、イタリア語オペラ)、モーツァルト《魔笛》(1791年、ドイツ語オペラ)、ビゼー《カルメン》(1875年、フランス語オペラ)と、使用言語も歌い方のスタイルも異なる3つの作品を取り上げました。
オペラの題材は、神話や歴史(《ジュリアス・シーザー》)、民話(《魔笛》)、小説(《カルメン》)等多岐にわたりますが、キリスト教の物語を用いるのはタブーです。しかし、先生のお話によれば、オペラの背後には、キリスト教に対する不信、または熱狂的信心が隠されているとのこと。
カストラート(去勢された男性歌手)が、元々は教会で女声の代わりを務める歌い手であったという事実と考え合わせると、オペラとキリスト教の複雑かつ深いつながりが見えてくるようです。
舞踊文化論
① オリエンテーション

コーディネーターでいらっしゃる、成城大学の國寳真美先生による講義でした。
文字記録の役目を果たしていたハワイアン・フラ(フラダンス)、死者を供養する日本の盆踊り、ニューヨークのサウスブロンクス地区で喧嘩の代替手段として誕生したブレイクダンス……世界にはこのように、踊る目的、国、文化などの違いから、色々な舞踊が存在します。
アメリカの心理学者が行った実験の結果によれば、身体言語(ボディランゲージ)は、言語以上に伝える力を持っているとのこと。
踊らない民族は居ません。
舞踊は、それぞれの文化、歴史、宗教等を反映した芸術なのです。
② フランスのダンスと文化

本学の岡見さえ先生による講義でした。
テーマは、バレエにはじまり、コンテンポラリーダンスに至るまでのフランスの舞踊の歴史についてです。
イタリアから伝わり、ルイ14世治下の17世紀フランスで花開いたバレエは当初、スペクタクルであると同時に、礼儀作法でもありました。実際、ルイ14世の有名な肖像画を観察すると、踊りの場面でないにもかかわらず、王の足のポジションは、踊るときと同じ状態になっています。
バレエを愛好し、自ら踊っていた王。王が踊るなら廷臣たちも踊らなければならないため、バレエは宮廷の男性中心のものでした、しかし、一般への普及とプロ化によって、女性のダンサーが増加していきます。
同時に、バレエそのものも変容していきました。18世紀には、台詞がなく、身振りだけでストーリーを進行させる劇的バレエ(バレエ・ダクション)が提案され、現在のバレエのかたちに近づきます。
19世紀にフランスのバレエは隆盛を極めますが、世紀の後半になると、人工的な動きをするバレエ(古典舞踊)に反発して、自然な動きの方が美しいとするモダンダンスが出現しました。そこから、ポストモダンダンス、ヌーヴェル(非ポストモダン)・ダンスを経て、ひとりひとりの美学を大事にするコンテンポラリーダンスへとつながっていくのです。
③ 実践者の視点からの現代舞踊

コンテンポラリーダンサーの川合ロン先生による講義でした。
コンテンポラリーダンスとは何かについて、プロのダンサーの視点からお話しいただきました。
伝統を引き継ぐタイプのダンスとは違い、コンテンポラリーダンスにおいて重要なのは、「創作」というプロセスです。
振付家のアイデアを体現するために、ダンサーには、振付の細かい「質」を創作する能力が求められます。
ワークショップでは実際に、コンテンポラリーダンスを体験しました。
驚くことに、先生から具体的なポージングの指示はまったくありません。
代わりに与えられた指示は、2人でペアを組んで、1人が相手に合わせて動くといった不思議なもの。
学生たちの表情が次第に豊かになり、動きも自由になっていったのが印象的でした。
④ 祭りの変化から見える日本社会

総合人間科学部社会学科の芳賀学先生による講義でした。
よさこい系祭りの起源と発展、祭りが抱える問題などについてお話しいただきました。
1954年に、戦後復興を目的として高知市の商工会議所が立ち上げた「よさこい祭り」。
急激に規模が拡大するにつれて、伴奏に『よさこい鳴子踊り』を一節入れれば踊り方も衣装も自由という、制約の少ないものに変化していきます。
1990年代後半以降、「よさこい系祭り」は全国に伝播しました。
伝播した地域での観光化によって、現在では、内容だけでなく、参加条件までが自由になっていますが、これは、単純に良いことだとはいえません。
かつて、祭りという行事への参加は、町内の住民の特権であり義務でもありました。外部の人間が自発的に参加する形態へと変わったことで、踊り手の実力や参加チーム数が安定しない、祭りに参加しなくなった地元民が、広範囲からやって来る参加者がもたらす騒音、渋滞、ゴミの被害に悩まされるといった問題が起きているのです。
⑤ ソマティック教育とボディワーク

保健体育研究室(2022年度以降、基盤教育センター身体知領域)の吉田美和子先生による講義でした。
ダンスとは何か、動くこととダンスすることの境目はどこにあるのかについて考えていきました。
考えるヒントになるのは、ダンス教育の方法です。
ダンス教育では、自分の身体を内側から視るというアプローチがなされています。自分の骨のイメージを描いてみるところからはじまり、外側から見える物としての身体(Body)ではなく、身体・心・スピリチュアリティを含むからだ(Soma)を探求するのです。
パリで活躍する有名なダンス指導者ピーター・ゴスのレッスン風景も、映像で確認しました。
ゴス氏のレッスン内容は、身体のなかの動きを教える、一種の体験的解剖学。
ダンスの奥深さを感じた時間でした。
⑥ 即興ダンス・ワークショップ

舞踊家の岩下徹先生をお招きしてのワークショップでした。
先生にとってダンスとは、「少しずつ自由になっていくこと」。
身体の緊張を解いた状態で横たわり、ゆっくりと身体を起こしていくという動きを何度も繰り返します。
最終的には、十分かけて、横たわった状態から立ち上がった状態になるようにという先生からのご指示が……。
テクニックは必要ないため、簡単そうですが、実はかなりしんどい動きです。日常生活において、起き上がるのに十分もかけるなんてことはありません。
自由になるのは難しいということと、自由になるためには自分の身体を知らなければならないのだということを学んだ体験となりました。
⑦ インドネシア・バリ島の舞踊
コーディネーターの國寳真美先生による、バリ舞踊についての講義でした。
バリ舞踊における所作や振る舞いには、それぞれ意味があります。
花を投げるのは場を清めるため、奉納の踊りの際に踊り手を抱いて舞台まで運ぶのは、地面にいる悪い神が身体のなかに入ってこないようにするためです。
奉納の踊りの映像のなかには、見物していた地元の女性がトランス状態に陥るシーンも……。
先生によれば、これは地元民の間ではよく起きる現象だけれど、観光客のような外部の人間が同じようにトランス状態になることはないそうです。
映像をとおしてではありますが、民族舞踊の神秘に少し触れることができました。
⑧ 日本バレエにおける移植と発展の特殊性

早稲田大学の川島京子先生による講義でした。
バレエダンサーの養成は、海外においては、国が一括して取りしきる国家的事業(適性によって志願者を厳正に選抜)ですが、日本では、いくつものバレエ団による利潤追求を目的とした民間事業(志願者すべてが入門可)です。
このような現状を生み出した原因は、「日本バレエの母」といわれるエリアナ・パヴロバ(1897-1941)が、彼女のバレエ・スクールにおいて日本古来の家元制度を採用し、弟子を数年で、次々と独立させていったことにあるというのが、先生のお話でした。
もっとも、日本のバレエ界には、バレエ向きの体つきでなくても才能を花開かせることができるという利点もあります。
顕著な例として、166cmと小柄でありながら、ボリジョイでキャラクター・ダンサーとして活躍した岩田守弘氏の軌跡を映像で辿りました。
映像芸術の世界
――映画産業を多角的に考える――
① イントロダクション

英文学科の松本朗先生による講義でした。
1980年代から1990年代後半にかけてのアメリカ、およびイギリス社会の変容(福祉社会から経済至上主義社会へ)と、1990年代に流行した大災害映画(ディザスター映画)とのつながりについて見ていきました。
講義のなかでは、特に、ローランド・エメリッヒ監督によるディザスター映画『インディペンデンス・デイ』(1996)に注目しました。この作品では、共通の利益(生き残り)のために皆が一致団結するという考えが示される一方で、自爆攻撃をさせられたケイスという人物の死が、最後のハッピー・エンディングで完全に忘れ去られる、という矛盾が起きています。
ディザスター映画は、新自由主義がもたらした競争社会の本質(自分の未来は、リスクを受け入れながら自分の手で切り拓かなければならない)の、アイロニカルな表現であるというお話でした。
② 映画のジャンル論~ミュージカル映画~

立教大学(2020年4月より京都大学)の仁井田千絵先生による講義でした。
1910年代後半から1960年代までの古典的ハリウッド映画の特徴と、新しいジャンルとして登場したミュージカル映画の構成について見ていきました。
古典的ハリウッド映画の登場人物は、二つの目標(恋愛や家族といった個人的な目標と、仕事や戦争といった社会的な目標)を持っていて、ストーリーは、ひとつの目標が達成されるともうひとつの目標も達成される、というように展開していきます。
ミュージカル映画は、上記の基本パターンを踏襲しつつ、二通りの方法――ストレート型(日常のなかの非現実、あるいは夢がテーマになっている作品)とバックステージ型(ショー・ビジネスの世界がテーマになっている作品で、歌と踊りは、映画内における舞台上演のかたちで登場する)――によってつくられているとのことでした。
③ 同性愛を扱う映画

溝口先生近影 (撮影:石黒壮明)
(「フューチャーコミックスPRESENTS~BL進化論サロン・トーク 特別篇〜ゲスト:萩尾望都先生 」2019年10月26日(土)にて。)
明治学院大学の溝口彰子先生による講義でした。
テーマは「レズビアン映画」。これまで映画で描かれてきた女性同性愛は、多くの場合、異性愛者の映画製作者が、異性愛者をターゲット観客層とし、異性愛規範の枠組みを脅かさない、もしくは補強するように利用する形だった、というお話でした。
少女同士の親密さは描かれても大人になるまでの期間限定であることも強調される『櫻の園』(1990)や、傷ついた異性愛者の女性を慰めるために奉仕するキャラクターがレズビアンであるといった設定(『カケラ』2009)には、大人のレズビアンは存在しないし、もしいたとしても、彼女は異性愛女性を癒すためのコマでしかない、という偏見が表れています。つまり、大人の女性同性愛者が、主体的に、恋したり悩んだりする様子は描かれてこなかった。
近年の例外として紹介されたトッド・ヘインズ 監督の映画『キャロル』(2015)は、1951年に発表されたパトリシア・ハイスミスの小説を原作としています。同性愛者が苛烈な弾圧を受けていた時代に、レズビアンがレズビアンとして生き抜いていくことを示唆するエンディングで、長年、数多くのレズビアン当事者たちを勇気付けてきた物語が、60年以上を経てついに映画化されたわけです。授業では、キャロル(ケイト・ブランシェット)とテレーズ(ルーニー・マーラ)がホテルの喫茶室で話しているところを、冒頭ではテレーズの知人の男性の視点から捉え、ラストでは、テレーズおよびキャロルという女性主人公の視線で見せながら、冒頭では描かれなかったその先までをも描くことで、より感動的になっていることが説明されました。主演2人が決まってからも、女性同性愛がテーマであるがゆえに、資金調達に時間がかかったことも英語圏では報道されていたそうです。そんな作品なのに、日本の配給会社によって、「レズビアン」という用語の使用を禁じられ、「美しい女性たちの愛」といった表現に直すように求められたという評論家の話を聞いて、先生はショックを受けられたそうです。それは、原作者や映画製作者たちの努力と勇気を踏みにじる行為、つまりは「文化を踏みにじる行為」であり、現実の日本のレズビアンの存在を無効化することでもあり、「オープンリー・レズビアンの研究者で教師である私には、とうてい許せるものではない」と断じた先生のお言葉が印象的でした。
④ フランス映画を考える

フランス文学科の吉村和明先生による講義でした。
テーマは「ヌーヴェルヴァーグ映画」。
ジャン=リュック・ゴダール監督による「引用の織物」としての『気狂いピエロ』(1965)と「映画批判」としての『東風』(1969)に注目し、映画作品のなかの「引用」はどのような意味を持つのか(『気狂いピエロ』)、映画そのものについて考えることは映画になるのか(『東風』)について考えていきました。
『気狂いピエロ』は引用にはじまり(エリ・フォール『近代芸術Ⅰ』のベラスケス論)引用に終わる(ランボーの詩「永遠」)作品で、ストーリーのなかにも多くの引用が登場します。
『東風』では、ハリウッド批判、メーキャップ(ごまかし)批判が、アジテーション(扇動行為)のように語られます。
講義冒頭での先生のお言葉「映画とはイメージの体験であり、新しい世界の発見である」の通り、非現実でありながら同時に現実でもあるような、不思議な世界を体験した時間でした。
⑤ 映像を分析する~ショットを読むということ~

明治学院大学の斉藤綾子先生による講義でした。
プロダクション・コード(映画製作倫理規定)の規制緩和とホラー映画流行という時代背景のなかで生まれたヒッチコック監督の映画『サイコ』(1960)を取り上げ、シーンを分析していきました。
盗みを働いたヒロインのマリオンは、シャワーを浴びている最中に、精神を病んでいる男ノーマンに刺殺されます。
注目すべきは「音」。マリオンが雨のなか車を運転するシーンでは、シャワーシーンで彼女が殺された後と同じ音が使われています。
浮かび上がってきたのは、切れ切れのストーリーを貫く、「罪を洗い流す」水のモチーフの重要性でした。
⑥ 映画とビジネスの関係

日本大学の古賀太先生による講義でした。
映画は、製作予算が大きいうえに、プロの評価より大衆人気に左右されることから宣伝費もかかるという、ハイリスクなビジネスです。同時に、ヒットすれば莫大な収益が得られるという、ハイリターンなビジネスでもあります。
昨今は、オリジナル脚本がめずらしくなっていますが、それも、小説や漫画作品等の映画化に比べて、認知度向上のための宣伝にお金がかかるという商業的な事情によるものです。
映画ビジネスの要である製作、配給、興行を邦画大手が独占している、プロデューサーの力が弱くて映画館の力が強いといった、日本の映画業界が抱える問題についても知ることができました。
舞台芸術の世界
① 舞台で役を演じる

ミュージカル俳優の石井一孝先生による講義でした。
ひとつの舞台がどのように作られていくかについて、貴重なお話を伺うことができました。
舞台稽古の期間は約四日、稽古中の伴奏は小さなグランドピアノかアップライトピアノのみで照明もなし(日本のミュージカルの場合)という事実には驚きです。
お話だけでなく、『ジキル&ハイド』からFirst Transformation とAlive! を、さらに、シンガーソングライターでもいらっしゃる先生が作曲を手掛けられたオリジナル曲「幕が上がれば」をご披露いただき、皆にとって幸せなひとときとなりました。
② シェイクスピア劇と英国史

英文学科の西能史先生による講義でした。
英語という言語の基礎を築いた天才と称されるシェイクスピアの『ジョン王』(1596年頃)に至るまでの英国史について見ていきました。
二週にわたる講義の第一週目だったため、『ジョン王』の中身については触れられませんでしたが、先生のおっしゃった、「文学作品を読むという行為は、すぐれた死者との対話である」という言葉が心に残りました。
③ 舞台芸術を支える

国際交流基金アジアセンターご所属の舞台芸術コーディネーター山口真樹子先生による講義でした。
文化紹介や人物交流というかたちで舞台を支えてこられた先生ですが、文化を「発信」するには、発信する相手のことも知らなければならない、交流とは双方向的なもの、といったことを常に考えていらっしゃるそうです。
東京ドイツ文化センターやケルン日本文化会館でお仕事をされていたご経験から、ドイツと日本の演劇システムの違いについてのお話もうかがうことができました。
④ 落語~噺家の演技~
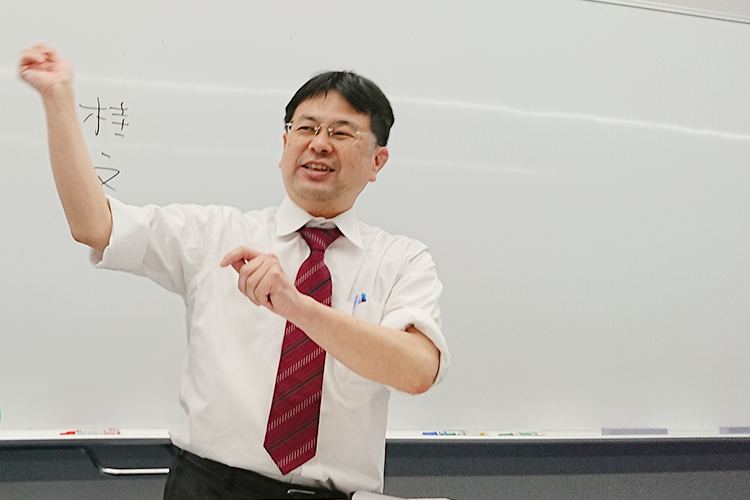
国文学科の福井辰彦先生による講義でした。
舞台装置は座布団一枚、小道具は手ぬぐいと扇子のみという、シンプルかつ味わい深い舞台芸術「落語」についてお話しいただきました。
目線、声の出し方、首の角度などで、空間の奥行き(家のなかのシーンであれば家の広さ)を表現するのが、落語の演技であるとのこと。
実際に、古今亭志ん朝『船徳』の映像を観ながら、演技に触れる時間もありました。
⑤ 歌舞伎を製作する
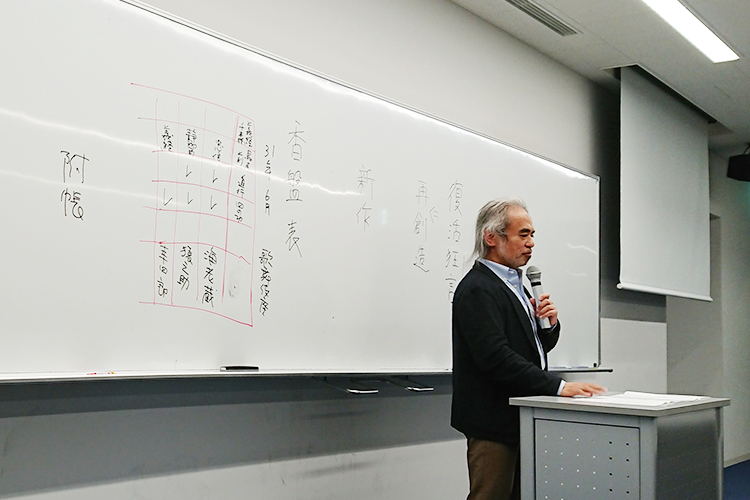
歌舞伎脚本家の今井豊茂先生による講義でした。
シェイクスピア原作の『NINAGAWA 十二夜』や、絵本が原作の『あらしのよるに』の脚本を手掛けられた先生からは、古典芸能のなかで新作がどのように生み出されていくかについての興味深いお話を伺うことができました。
『NINAGAWA 十二夜』での、紗幕の代わりに鏡を使用した演出、歌舞伎史上初の、動物しか舞台に登場しない『あらしのよるに』。いずれも斬新な試みですが、舞台稽古や小道具の作成の手順は、古典演目のときとまったく同じだそうです。
こうした童話やシェイクスピア劇の歌舞伎化は、かつての、文楽『仮名手本忠臣蔵』の歌舞伎化と何ら変わらないプロセスを辿っているというご説明もありました。
⑥ 文学と音楽劇

フランス文学科の博多かおる先生による講義でした。
メリメの原作をもとにしたビゼーのオペラ『カルメン』(1875)の演出効果について、公演が収録されたDVDを観賞しながら考えていきました。
カルメンが舞台に登場するときに歌う有名なアリア「ハバネラ」は、当時の流行歌を素材にして作られたものです。
他にも、カルメンが恋人のホセに赤い花(ホセの保守的価値観と対をなす価値観の表象)を投げる、伍長であるホセにとっては秩序の象徴であるラッパの音を、カルメンが伴奏代わりにして踊る、といった演出によって、ロマであるカルメンの人物像が巧みに表現されていることがわかりました。
⑦ 劇の台本をつくる

舞台演出家、脚本家、翻訳家でいらっしゃる木内宏昌先生のご登場です。
先生が現地で鑑賞された、ルーマニアのシビウ国際演劇祭の模様についてのお話から講義ははじまりました。
ルーマニアの巨匠シルヴィウ・プルカレーテ演出の作品は、舞台芸術とは何かについて改めて考えさせられるような不思議な世界観をわたしたちに提示します。たとえば、『ファウスト』では、観客が席を立って、地獄を観に行くツアー(セット裏)に参加したりするのです。
「舞台の台本」とは何か、「台詞」とは何を観客に伝えるものなのか、等についても考えていきました。
⑧ 総括~ドラマトゥルギーとは?~
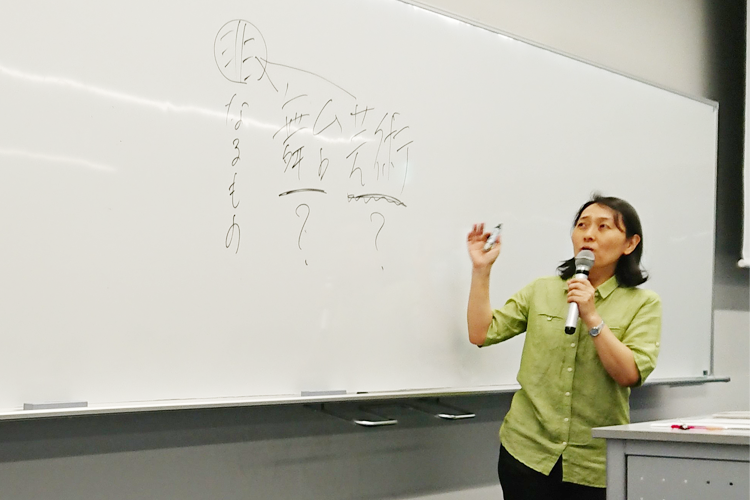
最後は、ドイツ文学科の三輪玲子先生による講義でした。
「ドラマトゥルギー」の元になっている「ドラマ」の原義は「ドラン(行動する)」。演劇は、行動に意味を持たせようとする側(上演関係者)と、行動の意味を汲みとろうとする側(観客)の両方が存在することによって、はじめて成立します。
「ドラマトゥルギー」には、具体的に、「作劇法、演劇論」、「戯曲の脚色」、「演劇制作部」といった意味があります。
日本ではあまり馴染みのない職業「ドラマトゥルク」についてのお話もありました。「ドラマトゥルク」とは、劇場所属の文芸部員のことで、シーズンごとに上演する作品の選定や上演台本の翻訳・改作・作成、演出への協力などを、主な仕事としています。
森鴎外が訳したグルック作曲のオペラ『オルフェウス』が、長いときを経てようやく舞台にかけられた際、鴎外の原稿をチェックし、修正するという重要な役割を担ったのは、日本人のドラマトゥルクでした。

